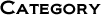2024年10月19日、20日の二日間、「O H!江戸東京まつり」の一環として、中央区で初めての流鏑馬が、堀留公園で開催されました。
本物の日本文化にふれる~日本橋・銀座で、ここでしか体験できない江戸文化体験イベント~と銘打って開催されている「OH!江戸東京まつり」の特別体験として小笠原流弓馬術・流鏑馬が行われました。
五街道の起点である日本橋で、流鏑馬を見ることが出来るなんて驚きました。
本来なら240メートルで的が3つのところを3分の1の約80メートル、的も1つに縮小されてはいましたけれど。
実はこれって、射手にとっては難しいのだそうです。ゆっくり走る方が大変とか。
それでも皆さん見事に的に矢を命中させ、的になる木が割れる音がビルの谷間に響いていました。惜しくも当たらなかった人もいないわけではなかったのですが、矢は的のすぐ近くを通っていました。
そしてその度に見ている皆さんの歓声が上がっていました。
流鏑馬といえば、神社の参道などで行われるもの、それが東京の中央区、ビルに囲まれた公園で行われたのです。
流鏑馬は、平安時代から鎌倉時代にかけて盛んに行われ、現代の形式が整えられたのは江戸時代中期、1724年に徳川吉宗の命を受けて小笠原家の二十代当主・貞政が制定しました。
この小笠原流宗家嫡男の清基氏の解説で、楽しく間近に見ることが出来た、貴重な体験でした。