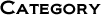🟡 「光の花の庭 〜フラワーファンタジー2025〜」(栃木県)
アメリカCNNが選んだ、世界の夢の旅行先10ヶ所に選ばれたあしかがフラワーパークで開催されます。
◆ 開催期間:開催中 〜 2026年(令和8年)2月15日(日)(休園日あり)
◆ 開催場所:あしかがフラワーパーク(栃木県足利市)
◆ 問合せ:あしかがフラワーパーク
園の象徴ともいえる大藤棚・奇跡の大藤には細部までこだわった花房を再現、本物の藤棚のような見応えです。
この大藤棚をはじめ、5000本の光のバラ、4色の藤をイメージした光のふじのはな物語、サンタクロースが空飛ぶ姿を再現し上空にはオーロラが登場するスノーワールド、水面に光が映る光のピラミッド、高さ25メートルのイルミネーションタワー、光の壁画やレインボーマジックなど、500万球以上のイルミネーションが園内を彩ります。
西ゲート前にはJR両毛線に新しい、あしかがフラワーパーク駅が開業し、電車でのアクセスも便利になりました。
🟡 「華厳ノ滝ライトアップ」(栃木県)
日本三名瀑の一つ華厳ノ滝がライトアップされます。
◆ 開催期間:2025年(令和7年) 11月15日(土) 〜 11月24日(月)
◆ 華厳ノ滝(栃木県日光市)
◆ 問合せ:奥日光観光事業振興会事務局(日光市観光協会日光支部内)
期間中の土日祝日には、ご当地ヒーローのグリーティングや和太鼓の演奏も予定されています。
また、中禅寺湖畔でも12月の中旬頃までイルミネーションの開催が予定されています。
🟡 「東京ドームシティ ウインターイルミネーション TOKYO SHOW DOMECITY」(東京都)
今年で21回目の開催です。
◆ 開催期間:2025年(令和7年)11月17日(月) 〜 2025年(令和8年)3月1日(日)
◆ 開催場所:東京ドームシティ(東京都文京区)
◆ 問合せ:東京ドームシティわくわくダイヤル
昨年の約65万球から、今年は大幅にスケールアップし、合計約100万球、スノードームや雪をテーマに、東京ドーム全体が白い光に包まれます。
🟡 「養老渓谷 紅葉ライトアップ」(千葉県)
関東エリアで一番遅い紅葉スポットとして知られる養老渓谷でライトアップが行われます。
◆ 開催期間:2025年(令和7年)11月23日(日 祝) 〜 12月初旬
◆ 開催場所:栗又の滝、懸崖境、中瀬遊歩道、山の駅 養老渓谷喜楽里(大多喜町) 観音橋(市原市)
◆ 問合せ:一般社団法人 大多喜町観光協会・市原市観光振興課
なお、2023年の台風接近に伴う大雨の影響で、一部立ち入り禁止の場所があります。
🟡 「上野村スカイブリッジイルミネーション」(群馬県)
自然豊かな癒しの観光地ともいわれる上野村で、群馬県内最大級となる約90万球のLEDを使用して開催されます。
◆ 開催期間:2025年(令和7年)11月29日(土) 〜 2026年(令和8年)3月9日(日)
◆ 開催場所:上野村スカイブリッジ(道の駅上野に集合の後マイクロバスで送迎)
◆ 問合せ:株式会社上野振興公社
高さ90メートル、全長225メートルの巨大吊り橋が幻想的に輝く光の架け橋となり、訪れる人々を特別な空間へと誘います。
*開催期間は、天候など諸事情により変更の場合があります。ご確認の上お出かけください。
以上