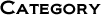先日紹介した三重テラスで行われている「みえの餅街道 in 東京」に行ってきました。
きっかけは単純に、甘いものが好き、だったのですが、「みえの餅街道」は、とても奥が深いものでした。
そもそも餅は、日本古来の伝統的な食品、というだけではないのですね。
餅を食べるのは、正月や様々な年中行事の時でした。つまり特別な時、ハレの日の食べ物なのです。餅を作るには大変な手間がかかります。今は、餅を家で作る方は少ないかと思いますが、以前は各家庭で、あるいは町や村での手作りがほとんどでした。手間がかかるから、特別な時しか食べることが出来なかったのでしょうね。
そんなことから三重の先人たちは、日本全国から伊勢神宮へお参りに来る人々に、餅でおもてなしをしたのです。長い道のりを歩いて来た人たちは、このおもてなしに、もうすぐ伊勢神宮だと思い嬉しかったでしようね。
そして餅は、コンパクトに栄養補給をしやすい食品でもあります。
精神的な面でも、肉体的な面でも、両方の意味で、餅は伊勢参りの方達を応援する食べ物だったのです。
正月の餅の形や味が、地方によって丸や四角があったり、醤油味や味噌味があるように、三重でもその土地ならではの餅があったのだと思います。それぞれの土地の餅でのおもてなしが、今のみえの餅街道のそれぞれの餅になっているのだと思います。
みえの餅街道、その感覚は以前からあったものの、実はこの言葉は昭和の時代には無かったようです。そう呼ばれるようになったのはまだこの20年ほどのことだとか、とは言いながらも、パンフレットやチラシに載っている約20店のほとんどはそのルーツを江戸時代まで遡ることが出来るとのことでした。
今回の「みえの餅街道 in 東京」のチラシに紹介されているのは、北は伊勢街道の出発点桑名の「安永餅」から、伊勢の店、そして南は志摩の「さわ餅」まで15店、それぞれ形も特徴、作り方も様々です。
私も、その中から伊勢の、伊勢といえばという冠がつく「赤福餅」と太閤秀吉の出世にあやかる縁起餅「太閤出世餅」の2種類をいただきました。
方や柔らかいお餅と上品な餡の組み合わせ、そしてもう一方は豊臣秀吉が好んで食べたと言われる焼餅で、小豆ともち米の旨味を引き出しているとチラシにありますが、まさにその通り、甘さの感じも、餅の食感も違うのです。
同じ伊勢でも、これだけ違う餅街道のお餅、機会があったら東京から歩いて行き、伊勢街道を神宮に向かいながら、一つずつ食べてみたいと思いました。
それにしても今回、三重の餅が単なるスィーツの餅ではなく、伊勢神宮があったから、そして伊勢参りという文化があったから発展したという事を知り、奥が深いと実感しました。
日本の各地にあるスィーツの街道、その中でMOKO/もこは今「みえの餅街道」が一番気になっています。
なお、今回の「みえの餅街道 in 東京」では、Mie Mu (三重県総合博物館)の学芸員・宇河雅之氏によるトークショーが行われ、宇河氏に色々なことを教えていただきました。
以上