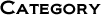ゴールデンウィークも終わったこれから混雑を避けて、どこかへ出掛けたいという方も少なくないでしょう。
そんな方々にお勧めなのが、春のバラ鑑賞です。バラというと、やはり女性にとっては憧れの花でもあると思います。関東地方には各地にバラの名所、またバラ園がありますが、その中でも特に気になる場所をご紹介します。
まず東京都内では、都立公園だけをみても都立公園ガイドによれば、あきるの市の自然の中のスポーツ公園・秋留台公園、千代田区のビジネス街のオアシス・日比谷公園、渋谷区の都心で一番広い空が見られる森林公園・代々木公園、北区の西洋庭園と日本庭園が調和・旧古河庭園、調布市の楽しんで学ぶ花の散策路・神代植物公園などが挙げられています。
中でも、注目したいのは、国指定名勝の旧古河庭園です。
JR山手線駒込駅から約10分という場所にありながら、その一画だけ別世界に来たように感じます。そして英国人建築家のジョサイア・コンドルが設計した洋館と洋風庭園、京都の庭師小川治兵衛が作庭した日本庭園を眺めていると時代すらも飛び越えてしまったかと思えるほどでした。
その洋館を見上げる階段状の庭園の第一テラスにバラが咲いています。
春と秋に約100種200株のバラが咲き、6月30日までは「春のバラフェスティバル」が開催され、特に5月10日から12日には、開園時間を1時間早め8時から入ることができる春バラの早朝開園も行われます。また、好評の春バラ人気投票や庭園ガイドも実施されています。
そして関東最大級のバラのテーマパークと言われるのが、千葉県八千代市の京成バラ園です。5月から6月上旬にかけては1年中で最も多くの美しいバラに包まれるトップオブピークを迎え、1600品種10000株のバラを楽しむことが出来ます。
ここでは「アリスのブルーミングカーニバル」が、6月16日まで開催されています。
また京成バラ園初の昼のパレードが、5月25日、6月1日、8日、16日に行われます。バラの植物園からバラのテーマパークへという京成バラ園ならではの賑やかで華やかというパレードが楽しみです。そしてもう一つ、この季節にしか見ることが出来ないのが、春バラのアーチ、その下を通るだけでウキウキしてきそうです。
また春は青いネモフィラで知られる茨城県の国営ひたち海浜公園でも、春バラを楽しめます。ローズレリーフガーデン、リラクゼーションガーデン、ハマナスの思い出ガーデンの3つのゾーンからなる常陸ローズガーデンでは、約120品種のバラが咲き、開花期間中はコンサートや現代バラ誕生の歴史を学べるガイドツアーも開催されます。
更に、埼玉県の伊奈町にも町制施行記念公園・バラ園があります。
ここには、伊奈町のバラ園のために作られたオリジナルの品種、真紅の大輪花のイナローズ、ツルバラで秋まで咲き続けるイナ姫、淡い黄色の中輪の花で柔らかく光る春の月を思わせる伊奈の月を始め400種5000株のバラが咲き誇り、5月31日まで「2024 バラまつり」を行っています。
また5月11日、12日には、全国29の市町が加盟する第33回ばら制定都市会議in伊奈が開催され、11日には、ばらサミット開催記念植樹式も行われます。
花の女王ともいわれるバラ、その種類は多いのですが、この機会に各地のバラの名所を巡り、それぞれ自分の好きなバラを見つけるのも楽しいと思います。
以上。